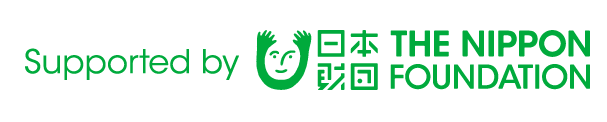【12の住まい】12:近藤秀夫さん
80代・ひとり暮らし
車いすユーザーの近藤さんは、この家が3 回目の建築だ。「自宅で何でもひとりでできるようにしたい」というコンセプトで、毎回、建築家の吉田紗栄子氏と、アイデアや好みの実現を話し合っている。車いすや介助なしに、寝室からトイレや浴室へひとりでアクセスできる工夫も。2階にはゲストコーナーを設けて、人を招く住まいとしても機能している。
→バリアフリー、住み替え、外出、五感リッチ、寝室、人を招く、ペット
「何でもひとりでできる」が、設計のコンセプト
近藤さんの現在の住まいは、2023年に亡くなった妻・樋口恵子さんの実家・高知県にある。自然豊かで新鮮でおいしいものがある、妻の故郷である高知で、のんびりふたりで暮らすのも悪くないと、東京から高知への移住を決断した。近藤さんが70歳を超えた頃だった。
いまはひとり暮らしとなったが、「何でもひとりでできるようにしたい」というコンセプトのもとに設計された住まいであるため、近藤さんひとりでも暮らしやすい工夫が随所になされている。
以前から仕事で海外や国内に行くことが多かった恵子さん。妻が不在でも、近藤さんが自由に家で過ごせるように、これまで新築や改築した家も、長年の付き合いであるバリアフリー建築家の吉田紗栄子さんと相談して設計してもらってきた。
恵子さんの姉がすぐ近くに住んでおり、個人的にお願いしているヘルパーさんがほぼ毎日訪れるため、近藤さんは、まわりのサポートを受けながら、80代になっても自立した暮らしができている。
 |
| リビングでくつろぐ近藤さん。吹き抜けと2面採光で明るく、20畳の広々としたリビングは、車いすがぶつかる心配もなく、ストレスフリー。 |
玄関からのゆるやかなアプローチ
動画でも紹介しているが、道路から玄関扉までのアプローチは、植栽豊かな庭を通り抜けて、ゆるやかなスロープ。外出しやすく、いつも緑に囲まれた住まいが実現している。
借景を取り入れた庭のデザインは、ガーデンデザイナー・環境デザイナーの正木 覚さんによるもの。
 |
| 庭の植栽がスロープの両側に配置され、森の小径を抜けて行くような感覚で出入りができる。庭から四季折々の自然を感じられる。縦樋に組み合わせて分岐し、雨水を取り出せる「パッコン」という装置を設置。庭の水やりに雨水が利用できるエコ仕様。 |
 |
| 玄関から室内への動線はすべてバリアフリー。車いすでそのまま乗り入れる。屋根には太陽光パネルを設置。一年中、床暖房やエアコンを入れて、常に一定の室温が保たれている。快適な室温管理は、ヒートショック防止としても大切な要素だ。 |
 |
| 室内から玄関を見たところ。車いすが移動できるスペースが充分にとってある。外のスロープからは、玄関以外にリビングの掃き出し窓やウッドデッキにも車いすで出入りできる。複数の避難出口が確保されているのも安心できる。 |
寝室からトイレ、浴室へは、ひとりで移動
トイレや浴室へのアクセスは、暮らしの中でも重要なポイントだ。寝室、トイレ、浴室をつなげ、床の高さを揃えることで、近藤さんが車いすなしでも、ひとりで移動できる動線を設けてある。
寝室からすぐトイレにアクセスできる動線は、Over 50’sの暮らしでも大いに参考にしたい点だ。
 |
| リビングに隣接した寝室。壁の引き戸を開けると、浴室・トイレへの入口となる。寝室、脱衣所、浴室、トイレまで、ベッドの高さに床面が合わせてあるため、ひとりでスムーズに行き来ができる。ベッドの右の壁面クローゼットは、手元にある道具(棒状のリーチャー)を使って、衣類を取り出せる。 |
 |
| 向かって左が浴室、正面が脱衣所、右が寝室への出入り口。ベッド横から渡されたスノコには車輪が付いていて、それを使って浴室まで移動。浴室の床から浴槽への移動動線も使いやすさが配慮されている。 |
 |
| ベッドからトイレへの移動が車いすなしでできることも、暮らしの質の向上となっている。床面からトイレ座面の高さが揃えてあり、ひとりで動作できる。 |
人が集まることを想定したリビング
「この家を建てるときに、僕の家には多くの人が出入りするだろうから、間仕切りなしでどのようにも使える20畳ほどの広さの部屋がほしいということを、建築家の吉田さんに最初にお願いしました。
これまでの家の設計をお願いしてきた長年のお付き合いだから、うちにどんな家具があるかまでをご存じです(笑)。引っ越すにあたって、新たに買った家具はありません。全部の家具がうまく収まるように設計してくれました」
 |
| 吹き抜けからリビングを見下ろしたところ。テーブルの横のチェストは、二段になっていたものを分けて低くしたもの。これも以前から使っていた愛用の家具だ。 |
 |
| 前の家から引っ越ししてきた食器棚。愛着のある家具を引っ越しの度に連れて来られるのは嬉しいことだ。床面は、1枚ずつ剥がせるコルクのタイル。傷んだところだけを交換でき、車いすで移動しても音が立たない。 |
 |
| キッチンはIHクッキングヒーター。換気扇が低い位置に付けられている。「この家では、ヘルパーさんや義姉が準備してくれるので、僕が料理をすることはないのだけど、車いすでキッチンを使えるように、高さや通路の幅を考えてあります」 |
2階には人を招くゲストルーム
2階には、ゲストルームとバルコニー。近藤さんが2階に上がることはないが、住まいの機能として人を招く場所があることは大切だ。
 |
| ゲストルームからバルコニーを見たところ。高台に位置しているので、見晴らしも素晴らしい。 |
 |
| 明かり取りの小窓のステンドグラスは、近藤さんが刑務所作業製品の販売所で購入したもの。 「近藤さんはいろいろなところから、いいものを見つけてくるので感心します」と吉田さん。 |
 |
| 2階から吹き抜けのリビングの様子を見おろすこともできる開放的な雰囲気。ゲストルームとして使うときは、ブラインドを引き下ろしてプライベート空間となる。2階にはトイレも用意されている。 |
思い出の品や気に入ったものに囲まれて
近藤さんは、思い出の品や気に入って見つけたものを、住まいに取り入れるのが好きだ。
部屋のあちらこちらにガラスや作家の作品、旅の思い出の品が飾られていて、居心地のよさを感じる。どの品にもそれぞれの物語があり、近藤さんがそのエピソードを語る姿も楽しげだ。
 |
| 1階のウッドデッキ。鍛鉄工芸家の西田光男さん作の、風見鶏ならぬ親父鶏。これも前の住まいから引っ越してきたもの。「鉄で重いから、風でくるくる回らないですけどね」 |
 |
| 1階リビングの柱に飾ってあるのは、近藤夫妻が買ってきた小樽のガラス。「吉田さんに、これをどこかに使ってほしいとお願いしました。鍛鉄の西田さんが鉄の枠飾りを作ってくれて、いい場所に収まりました」 |
家づくりに熱心な近藤さんは、建築家の吉田さんとふたりで、新しい住まいのために、ショールームを回ったり、兵庫県の西宮まで古材を買いにいったりと、手間暇をいとわず家づくりを楽しんだそうだ。
建材も小物も、自分で見に行って探すのが楽しいという近藤さん。家づくりを人任せにするのではなく、積極的に関わって、「自分の住まい」をつくりあげてきた。
 |
| いまはほとんど使われていないが、1階から2階への簡易リフト。四面の壁に、旅先のお土産や手作り作品など、思い出の品を飾っている。 |
外へ出なくても受け取れる郵便受け、小さな工夫が住み心地をよくする
 |
| 道路に面した郵便受けは、納戸に直結。外へ出なくても、部屋の中で郵便を受け取れる。近藤さんが手に取りやすいように、郵便受けは低い位置に。 |
近藤さんの自立を支えるHomeとまわりの人々
 |
| ウッドデッキでのひなたぼっこが気持ちよさそうな猫のひめちゃん。ペットのいる暮らしも、近藤さんの癒やし。 |
「女房が亡くなったときにね、僕はもう施設に入ろうと思ったの。僕は、人生の中でかなり長い間、施設で暮らしていたから、生活の場を自分の家から施設に移すことにも、あまりこだわりはなかった。だから、単純にそう考えた。ところが義姉やヘルパーさんたち、まわりの人がね、『車いすで不自由なく暮らせる家があって、ちゃんと生活できているのだから、なにも施設に入らなくてもここでいいじゃないか』と言ってくれてね。そうか、それならこのままここで住むか、と思い直しました」
すぐ近くには、義姉家族の家もある。お願いしているヘルパーさんは、実は庭の設計を依頼した庭師さんの妻。ヘルパー資格を持っているが介護保険のヘルパー仕事は制約が多くてしていなかったが、初対面で車いすを押してくれる介助があまりに適切で素晴らしかったので、自薦ヘルパーとして来てもらうことにして以来のご縁だ。
義姉や気心の知れたヘルパーさんが手助けし、支えてくれていることで、近藤さんの暮らしは心豊かなものになっている。
愛着のあるものや親しい人に囲まれた、素敵なhomeだ。
最後まで自宅で暮らしたいというのは、多くの人の願いである。
ケアリングデザインが75歳以上の男女を対象に実施した調査でも、「自立して暮らすことが難しくなった場合、住まいをどうしますか?」という質問に、「現在のまま住み続けたい」と回答した人は、自立シニアでも低自立シニアでも60%以上だった。
近藤さんの場合は家づくりの最初から「自立して暮らす」ことをコンセプトにしていたため、ひとりになっても暮らし続けることができる、心身ともに支えてくれる安心な住まいとなっている。
車いすで暮らせるバリアフリーの住まいの工夫が、一般住宅にも積極的に取り入れられていけば、自宅で暮らし続ける願いはかなえられるのではないだろうか。
車いすでも、そうでなくても、若くても老いていても、誰もが同等に楽しく暮らせる住まいが、ほんとうの意味でのバリアフリーとなるはずだ。
【プロフィール】
近藤秀夫さん
戦中に親を失い、戦後16歳のときに炭鉱で大けがをして障がいを負った近藤秀夫さん。1964年、東京パラリンピックの選手として活躍。その後、車椅子のケースワーカーとして、東京・町田市で20年以上活躍し、地域を変革してきた。妻の樋口恵子さんは、日本の自立生活運動のリーダーとして基礎を形成し、国政にも挑んだ。2023年に逝去。現在は、亡き妻の郷里・四国でひとり暮らし。ふたりの活動は、田中美絵子著『障がいを恵みとして、社会を創る 近藤秀夫と樋口恵子』(現代書館)に詳しい。
著書『車椅子ケースワーカーの7600日―私が福祉のしごとから学んだこと』(自治体研究社)
撮影:砺波周平