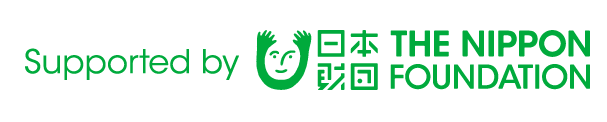暮らしのルールはお互いの領域を守ること
【12の住まい】02:かみて理恵子さん
60代・ふたり暮らし
20年程前に、郊外の広い2LDK から都心のコンパクトな1LDKマンションへ、1/2 にサイズダウンした住み替えを実行した、かみてさん夫妻。散歩や買い物、趣味の活動に、都心のアクセスビリティのよさを満喫している。引っ越し時にドイツ製のシステム家具を導入して、収納については徹底的に工夫を施した。ソファーに座る位置も収納の位置も、ふたりの区分を設けて、互いの領域には干渉しないのがふたりの暮らしのルールだ。
→サイズダウン、都心の利便性、外出、趣味、照明、物の整理、思い出の品
郊外から都心のコンパクトマンションへ、1/2のサイズダウン住み替え
結婚後、最初に購入した住まいは、千葉の3LDK・88㎡のファミリータイプ、オーシャンビューの新築マンション。購入して10年後に、3LDKから2LDKに間取りを変更し、2面バルコニーのメリットを活かして、浴室まで外光が届くようにするなど、思い通りのリフォームを行った。
ふたりが住み替えを決めたのは、20年ほど前のこと。夫の和巳さん50歳、理恵子さんが41歳のときのことだった。
会社員として忙しく働いていた時期だったが、夫の和巳さんはすでに定年後の暮らしを視野に入れていて、定年後は交通機関や公共施設・医療施設が整った都心に住むのがいいのではないかと、ふたりで話し合って決めた。理恵子さんも当時は管理職として忙しく、タクシーで千葉のマンションまで帰宅することも多かった。
リフォームまでして気に入っていた以前のマンションは賃貸に出し、都内のコンパクトマンションに住み替えた。
「今から考えると、定年後に住み替えるより、ふたりの気力も体力もあるうちに、引っ越しという大きなイベントを済ませておいてよかったと思います」
ドイツ製のシステム家具ip20を造り付けで導入
 |
| 1LDKの部屋は、右がリビングダイニング、左が寝室。寝室との境の引き戸は開いたまま、広々と使っている。 |
ふたりが選んだのは、1LDKのコンパクトマンション。築地市場や銀座が徒歩圏。どこへ出かけるにも便利なロケーションだ。
3LDK・88㎡から1LDK・46㎡へ、1/2のサイズダウンということもあって、荷物はかなり処分した。
「本当に必要なものかどうかを取捨選択して、ものと向き合う時間にもなりました。結局、半分位のものは使わないものでした」
いっぽう新居には、ドイツのシステム家具ip20を導入。テレビボード、キッチンのカップボード、寝室の棚など、すべてに造り付けの収納を設置した。
システム家具によって床から天井までの高さを最大限に収納に活かし、奥行きのあるクローゼットは前後のスペースをフル活用。
「一戸建てと違ってマンションは平面移動だけですので、間取りと生活動線を考えてものを配置すれば、片づけもしやすくなります」
 |
| 寝室のベッドには、あえて90㎝幅のマットレスを2台並べた。ベッド下は収納になっていて、理恵子さんの着物が収められている。ベッド上の棚と、向かって左の鏡裏もip20の収納。ベッド上は籠好きの理恵子さんのコレクションが並べられている。 |
理恵子さんは、現在ライフオーガナイザーという片づけのプロとして、独立して仕事をしている。
「もともとは片づけは苦手。でも、私が50歳で会社を辞めて時間ができて、住まいやものと向き合って片づけを始めたら、楽しくなって。そこから、“空間と思考の整理術”であるライフオーガナイズの手法を学び、片づけが習慣化するようになりました」
ソファーも棚も半分っこ
 |
| ベッドはマットレスの境目がそれぞれの領域の目印。「真ん中の線が重要。陣地争い、うちはシビアですよ(笑)」 |
現在、理恵子さんはライフオーガナイザーとして働き、夫の和巳さんは定年退職して自由な時間を楽しんでいる。
ふたりで過ごす時間が増えたことにより、暮らしのルールも自然と出来上がってきた。
「ベッド、ソファー、ローテーブル、テレビ台の棚は、左右でふたりの領域が決まっています。そこは相手の領域だから干渉しないというのが自ずと決まっています。観たい番組の趣味が違うから、実はブルーレイレコーダーも2つあるんです(笑)」
 |
| 以前のマンションから持ってきた、アルフレックスのローテーブル。テーブルも左右でふたりの領域が分かれている。左が理恵子さん、右が夫。 |
「あと10㎡あったら、わたしの仕事のデスクが広げられるかなと思うこともあるけれど、彼はそこまで狭さが苦にならないタイプ。限られたスペースで一緒に暮らしていくためのお互いのルールというか、お互いを尊重する生活が自然に出来上がっていきました」
もうこの住まい以外に住むことは考えられない。そう考えて、賃貸に出していた以前のマンションも、ふたりで決めて売却した。
 |
| アルフレックスの3人掛けソファーも、以前のマンションから厳選して持ってきた家具のひとつ。「新婚時代から、ボーナスが出るたびに少しずつ買い足してきた家具だから思い入れが深くて。特にソファーはこの部屋には大きすぎるかと思いましたが、やっぱり持ってきました」数年前には、古くなったクッション材と表地を張り替えた。「これが最後の張り替えかなあと思って」 |
ソファーとローテーブル以外に持っていたアルフレックスのダイニングテーブルセットは、実家に貰ってもらった。
「椅子や家具はいいものを選んで買っていました。甥っ子が結婚するときに、私たちが新婚時に買った椅子をもらってくれて。もらってくれたこと自体が嬉しかったですね。もう2脚残っている椅子は、姪っ子に『もらってね』と言ってます。思い出深い家具だから、弟の子どもたちが譲り受けて使ってくれることが嬉しいです」
 |
| ip20の造り付けの家具は、収納棚兼テレビ台として活用。床から天井までが有効活用されている。 |
 |
| 扉を開けたところ。左右のタテ一列が夫婦それぞれの領域。中央は、共有のものが収められている。自分のものは自分で管理。相手のものには勝手に手を出さないのがふたりのルール。 |
 |
| ダイニングコーナー。奥のキッチンとの仕切りにもip20の棚が設置されている。ガラス棚のグラス類は、キッチンからもダイニングからも取り出せる仕様。「シンデレラフィットという言葉もない頃に、雑誌でip20のシステム家具のことを知りました。入居前に導入しておいて本当によかったです」 |
 |
| ノウルェーのテリエ・エクストレムがデザインしたバランスチェア「EKSTREM」。寝室の隅に置いて、小さな読書スペースになっている。ほかにもYチェアなど、家具好きの趣味が垣間見える。 |
キッチンにはスマートデバイス、関節照明もアレクサで操作
 |
| コの字型で使い勝手のいいキッチン。向かって右の食器キャビネットもip20のもの。 |
 |
| キッチンのテーマカラーはレッド。アレクサのスマートディスプレイは、調理中にレシピを呼び出すのに活用している。ほかにリビングの照明もアレクサでコントロール。「料理していて、あれ、三杯酢の配合ってどれくらいだっけ?みたいなこともキッチンのアレクサに聞けるのが便利ですね」 |
ふたりとも、間接照明を好むタイプ。天井から一律に照らすのではなく、室内のあちらこちらに部分照明を取り入れている。
「夫の方が間接照明好きですね。食事も、ふつうの家庭よりかなり暗い照明で食べていると思います。でも、たとえば私が趣味の編み物をしようとすると、スタンドライトだけでは手元に影ができて思うように見えない。最近、ヨーロッパ旅行に行って見つけたのが、このライト付き老眼鏡。編み物をする手元だけをピンポイントで照らせます。これだ!と思いました(笑)」
 |
| イタリアで購入したライト付き老眼鏡。「5〜7ユーロ位で、もっと買ってくればよかったと思うほど、愛用しています」 |
ふたりの旅の思い出は食器やマグネット
今の住まいは、成田や羽田、東京駅にアクセスがよく、気軽に旅に出るには絶好のロケーションでもある。
ふたりは、国内でも国外でもいっしょに旅に出る時間を大切にしている。去年は、1ヶ月ほどヨーロッパ旅行に出かけた。
「旅先でもアパートメントに泊まるようにしていましたけど、1ヶ月も旅して帰ってくると、『ああ、やっぱり自分の家はいいなあ』とつくづく思いました。住まいって、自分たちを守ってくれる場所でもあるし、心の拠り所でもあるんですね。」
 |
| 旅先ではよく食器を買って帰る。大分で買った小鹿田焼(おんたやき)の皿は、タクシーに乗るときに落として粉々に。自分で金継ぎして復活させた。バルセロナの皿、ヴェネチアのグラス、香港の急須。「我が家の食器の半分位は旅先で買ったものです」すべての食器に旅先の思い出が詰まっている。 |
|
|
| 夫の定年後は、国内外問わず長期の旅行に出かけられるようになった。食器以外には、旅先でフリッジマグネットを買って冷蔵庫の扉にコレクションしている。旅の思い出が見えるかたちで並んでいるのがいい。 |
年齢を重ねるほどに、便利さが重要になってくる
「年を重ねると、便利さは重要ですね。夫は70歳を超えたから、都バスのシニア乗車券が使えるようになりました。でもここからだと、歩いてどんなところへも行けるので健康にもいいです」
ふたりでお弁当を持って皇居前の芝生でピクニックしたり、あちこちの街を歩いて訪れたりすることも、ふたりの共通の趣味だ。食や歌舞伎好きな理恵子さんは歌舞伎座へも、築地の場外市場の買い物へもすぐ歩いて行ける距離に満足している。
 |
| 近隣の区立図書館や国立国会図書館の貸し出しカード。図書館まで散歩がてら歩いていくことも、ふたりの楽しみのひとつ。「図書館ごとに本の品揃えが違うから、あちこちの図書館に通っています。夫は、ほぼ毎日図書館に通っているかも」 |
以前のマンションでは、1部屋が物置になっていたそうだ。引っ越しにあたって処分の判断がつかないものは、マンション近くにしばらくトランクルームを借りて収めていたが、それも処分して解約したという。結局それまでに持っていたものの半分は不要なものだとわかり、いまは自分が持っているものをすべて把握できているという。ものと真摯に向き合うという意味でも、住み替えは大きな岐路となったようだ。
「この住まいに暮らして20年経ちました。実家以外では、人生の中で一番長く住んでいる住まいになったかもしれません。引っ越したときは、ここが終の住処となるとは考えていませんでしたが、もう引っ越すつもりはありません。ふたりとも、自分のしたいことができる住まいに満足しています」
住まいは、何を優先順位にするかで選び方が変わってくる。
かみてさん夫妻は、広さよりも便利なロケーションを選ぶことで、その後の暮らし方がより充実した例だ。
何より、早い時期の住み替えの重要性を痛感させる。
【プロフィール】かみて理恵子さん
アパレル、IT企業に25 年間勤務。退職をきっかけにライフオーガナイズと出合い、資格を取得。2015 年に「収めるしくみ研究所」を設立。ライフオーガナイザー® としてセミナーやコンサルティングを行うかたわら、ウェルビーイング講座も開催している。
収めるしくみ研究所 https://osamerulab.com/
撮影:三村健二